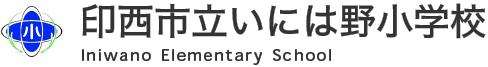道徳の学習の中で、自分の考えを伝えたり友達の考えを聞いたりするときに、
ICTを活用できないかと考え、「心と心のあく手」の授業を行いました。
教材を読むときに、教科書を使用せず、教科書の内容をロイロノートで全員に配信することで机上を整理した状態で授業に臨むことができました。また今回は児童の考えを表現させるときに、ロイロノートスクールの思考ツール「座標軸」を使用しました。主人公が、重い荷物を持っているおばあさんに「声をかける」「声をかけない」で葛藤している状況をふまえ、自分だったらどうするか、について考え、座標軸のどのあたりに自分は位置しているのか、またその理由を記入しました。
友達と交流するときには、ロイロノートスクールの比較機能を利用したことで、グループの友達と比べながら話し合うことができたのではないかと思います。
最後に「心と心のあく手」とはどういうことかを考えたときには「気持ちが一致すること」「心と心が合わさること」だという意見がでました。
そこから、本当の親切とは「相手の立場や気持ちに寄り添って、相手にとって本当に必要なことは何かよく考える」ということに気づくことができました。
児童のふりかえりには、「ただ優しくするのではなく、相手の気持ちを考えたい。」「友達の気持ちを考えてから、手助けしたり声をかけたい。」「見守ることも親切だとわかりました。」と書かれていました。
これからも、児童の考えを表現するときに効果的な思考ツールを考えながら取り組んでいきたいと思います。

7月7日 第3回校内授業研究会
ひかり学級1~4組 自立活動 「なかよし会を開こう」
「相手の立場になり、相手に分かりやすい指示の出し方、伝え方ができる」ということを目標に、1・2組は「わたしはだれでしょうゲーム」、3・4組は、「きょうりょくふくわらい」という活動に取り組みました。
支援級の児童の「書くことや人前で話すこと」等の困難さを克服したり、軽減できるICT活用は、児童の可能性を広げることに役立っていることを感じました。
ICTを活用することで、学習や発表することへの抵抗感が少ないことも感じられます。また、仲良く教え合ったり、考えや思いを交流し合えたりすることができることも良さであります。
今回の授業では、異学年の児童が、適材適所で活躍し、自信をもって楽しく学ぶ姿が見られました。
ふくわらいなど、作品が残せない物でも写真に撮って、大型ディスプレーで見合ったのもよかったです。一つ一つ提示していたゲームのヒントを、最後に一気に提示できたのも,ICTのよさです。
これからも、積極的にICTを活用していき、子ども達のできることを増やし、自信につなげていきたいです。

音楽科では、ベートーベン作曲「運命」の鑑賞を行いました。はじめに、電子音で作られた演奏を聴き、スコアや指揮者の役割について理解を深めました。さらに、2人の指揮者の演奏を聴き比べ、指揮者は、作曲者の思いを「受け継ぐ」・聴衆(児童自身)に「伝える」役割を担っていることに気づかせました。さらに、それぞれの指揮者の演奏から聴き取ったことをピラミッド型のシンキングツールまとめ、演奏の中で際立っていた特徴は何かについて、共有ノートを使って話し合いました。その後、資料箱の音源を使い、聴き取ったことの根拠となる演奏を切り取って聴き合うことで、感じた事と演奏を密接につなぎ合わせることができました。音源を何度も繰り返し聴いたり、2人の演奏を比べたりする事は、音楽を深く聴く事の一助となりました。

第3回校内授業研修会
ひかり学級1~4組 自立活動「なかよし会を開こう」
コミュニケーション力に弱さがある子どもたちは、人の立場や気持ちを察して、行動をとることが苦手であることから、今回は、ICT機器を活用して人と協力し合う活動を通し、「人と合わせる」スキルを身に付けさせることを意識して授業を行いました。
ひかり学級1・2組の「私はだれでしょうゲーム」においては、、一人一人がクイズやヒントを考えました。ロイロノートを使うことで低学年の児童でもクイズの作り直しなども容易に行うこともできました。また、できたクイズを高学年児童がスライドに作り直し、1年生でもわかるように文字の表記を工夫するなど、相手を意識した姿が見られました。クイズの発表時にはスライドの映像と言葉を合わせることで相手にわかりやすく伝えることができました。人との関わりを苦手とする児童にとって、ICT機器はコミュニケーションアイテムとしても有効であると感じました。
ひかり学級3・4組「きょうりょくふくわらい」では、ルールを守って遊ぶことの大切さを学び、ゲームの練習をすることをねらいとして取り組みました。
自分のめあてや振り返りをロイロノートやフォームスを活用して行いました。ロイロノートでは、高学年が低学年に使い方を教える姿も見られ、仲良く活動することができました。フォームスは、選択式の振り返りにしたので、短時間で行うことができ、メリットを感じました。これからの活動にも取り入れていきたいと思います。

7月7日 第3回校内授業研究会
4年2組 道徳科 「心と心のあく手」
「心と心のあく手」という資料を用い、「本当の親切とは」について、ICTを活用しながら考えていきました。机上にタブレットのみを置いたことで、机の上がすっきりとし、学習に集中できていました。
・大型ディスプレーを活用したことで、アンケート結果や、友達の考えや動画視聴など、全体に周知させたいことを集中して見せていました。
・座標軸を使って、全ての児童が自分の考えを表示できました。また、画面共有したことで、友達の考えを知ることもできました。
・比較機能を活用し、少人数で自分の考えと、友達の考えを共有した後、全体で話し合ったことで「本当の親切とは、根底に相手のことを思う気持ちがある。」「相手の立場や気持ちに寄り添って、よく考えることが大事だ。」と、さらに考えを深めていました。
・フォームスを活用し、学習の振り返りをすると、今日の児童の学びや考えが即座に示されるのもよかったです。
・道徳としての話し合い活動と、適切な場面での効果的なICT活用のバランスがよい学習でした。

7月8日 愛3回校内授業研修会
6年1組 音楽科 「演奏のみりょく」
ICT機器を活用し、演奏者の思いを感じ取って聴く事に興味を持ち、主体的・協働的に学習に取り組み、オーケストラの音楽に親しむことを目標に授業が展開されました。
ロイロノートのシンキングツールを活用するとともにICT機器に音源を取り込み、自分の選んだ部分の演奏を繰り返し聴き、音から指揮者の楽曲への思いを感じ取り友達と考えを伝え合うことができました。
研究協議では、音源をICT機器に取り込むことで、自分が選んだ部分を細かく相手に伝えられるよさが感じられました。また、共有ノートを使うことで意見交換をしながらリアルタイムで編集できていました。提出箱を細かく分けることにより、見たいノートをすぐに開くことができるよさもありました。
講師の先生からは、ICT機器に音源を取り入れることで、今までのような一斉での鑑賞でなく個別化への対応ができることやICT活用の効果は、利用機会 × 時間 × 技能で表されるということでした。


6月23日(木) 第2回校内授業研究会
6年2組 「特別の教科 道徳」
学校生活をさらに良くしていくために、自分にできることは何かをロイロノートを活用しながら話し合いました。登場人物の心情の変化や、自身の考え等をロイロノートに書かせ、全体で共有しました。児童は、友達の考えを読んだり、聞いたりして、自分にはなかった考えを見つけたり、考えを深めたりすることができているようでした。ICT活用をすることで、聴覚だけではなく、視覚的にも友達の考えを聞くことができました。また、考えを書くことが苦手な児童でも、ロイロノートだとスムーズに書くことができていたので、活用する良さだと感じました。
研究協議会では、ICT活用することで「共有」がこれまで以上に質の高い活動になると話がありました。また、これまでノートに自分の考えを蓄積していたが、ICT機器では1台にほぼ無限にできることも良さの1つだとも話がありました。しかし、使うことを目的にしてしまうと、本来の目的に迫ることができなくなってしまうと指導がありました。ICT機器の適切な活動方法として、それらを通して何を学ばせるかが一番重要になっていくのでは、ということが一番の課題であると話し合いました。今後、道徳はもちろん他教科でも、ICT機器の活用の仕方の工夫を考えていきます。
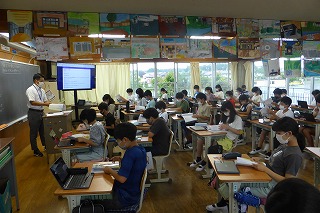
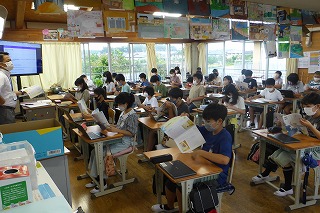
6月23日 第2回校内授業研究会
4年1組 道徳科 「ぼくの父さん」
ロイロノートの特徴を生かしながらICT機器を使った話し合い活動をさせ、児童の道徳性の向上をねらった授業が展開されました。
自分の考えを色分けしたテキストカードに書かせ、色別の提出箱に提出させることで、自分と同じ考えの人や自分と違った考えの人の考えを共有しやすくし、考えを深めさせることができました。
研究協議では、児童のICT機器の使い方やタイピング技能の高さが話題になりました。ロイロノートを工夫して使うことで、児童同士が考えを共有する時間を短縮できることや、発言が苦手な児童も自分の考えを表現しやすくなることなどがあげられました。また、話し合い活動時におけるICT機器の活用のさせ方が課題としてあげられました。
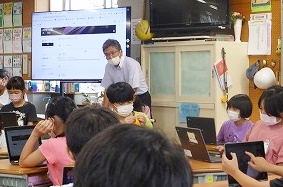

授業者①
6年1組では、算数科「分数のかけ算を考えよう」の授業を行いました。
1組教室と学年ルームの2つにわかれて学習しています。
長方形の面積 縦 横の長さが分数の時でも公式が使えるかどうかを考えます。発展では、直方体の体積でも考えました。
ロイロノートを活用し、数直線や面積図で示しながら式や説明をして思考を深めます。画面を共有しながら友達の考えや表現を理解し、学び合いました。
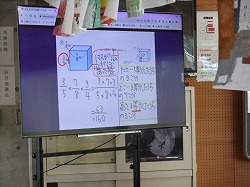

授業者②
「分数のかけ算をしよう」の学習では,単元を通して段階を追いながらロイロノートを活用しました。教師側から一斉に問題やヒントを配ることができたり,児童から提出された考えをすぐに共有できたりすることで効率的に学習が進みました。紙のノートよりも簡単に考えを書き換えられたり,色を付けて工夫して示すことができたりするため,試行錯誤する場面が多く見られ効果的に学習することができました。
各学年ごとのクロムブック活用事例の紹介とロイロノートでの印刷の仕方の実技研修を行いました。
〈クロムブック活用事例〉
1年生……パスワードの入力の仕方・写真撮り方
2年生……手書き入力の仕方・野菜の観察カード作成(生活)
3年生……グーグルスライドを使っての一日の流れの確認(掃除の様子など)
4年生……作品の提出の仕方(図工)・外国語や道徳での振り返り
子ども部屋を利用しての係活動の取り組み・体育での動画撮影
5年生……ジャムボードを使っての情報ノート作成(国語)
外国語でのデジタル教科書使用・社会と算数の宿題
6年生……自分が作った枕草子の紹介(国語)・クリーン作戦の活動記録(家庭科)
ひかり……外国語でのデジタル教科書の利用・ロイロノートでワークシート活用(社会)
音楽専科…グループ発表の共有
各学年等でのクロムブックの活用例が紹介されました。
〈実技研修の様子〉
ロイロノートでの印刷の仕方を研修しました。


職員のエピペン研修会を実施しました。
食物アレルギーについての共通理解もしています。


●エピペンはグーで握ります
●太ももに当ててから、力を入れて打ちます
職員研修として「不審者対応避難訓練」を実施しました。
子ども達の安全を守るために、どうすれば良いかを考えたり役割を確認したりしました。